LLMO対策のやり方を解説!SEOとの違いとSGE対策
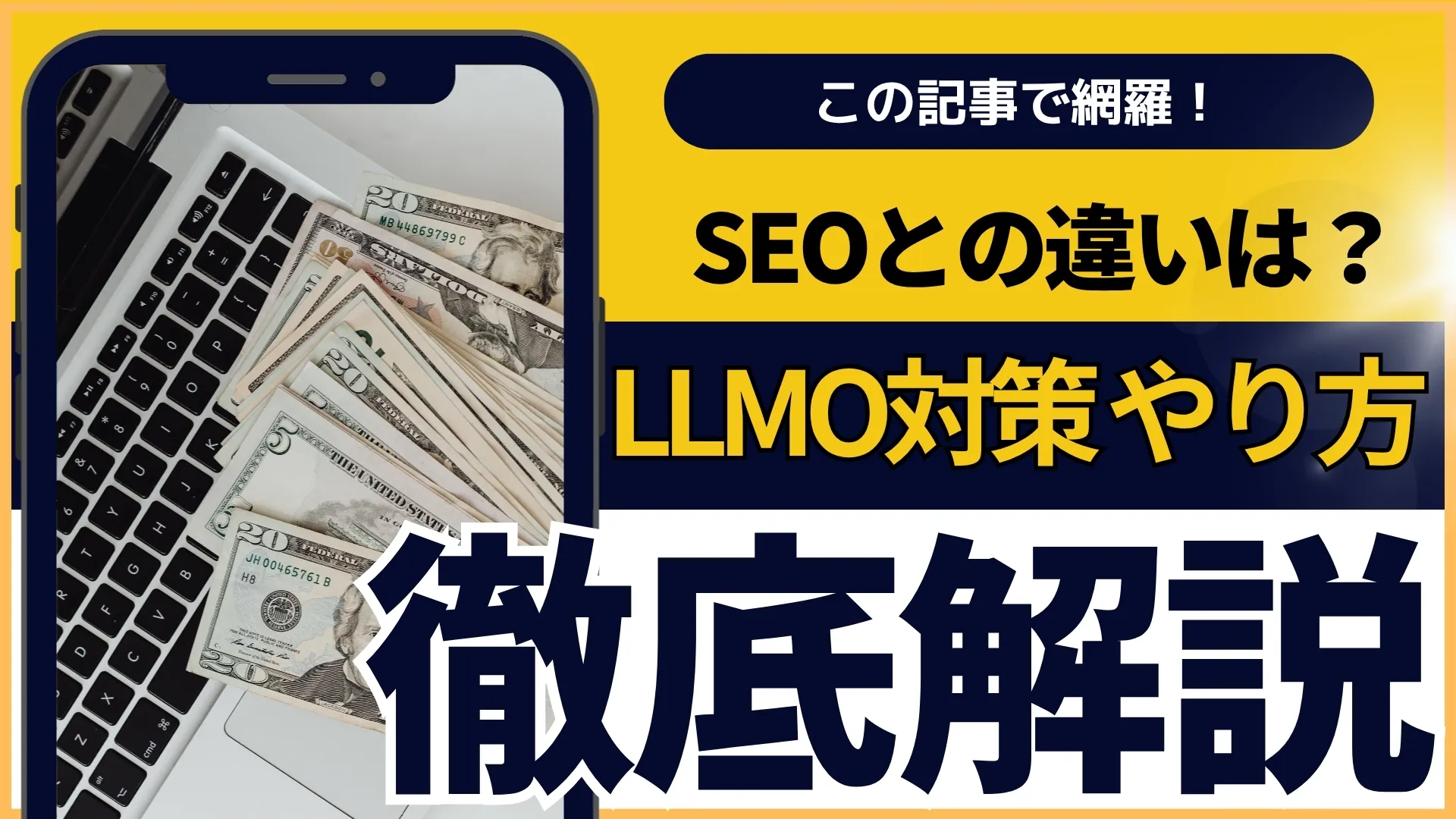
こんにちは。hakubi code 代表のてらだです。
最近、「LLMO」という言葉をよく聞くようになったけど、LLMOとは一体何なのか、従来のSEOとの違いがよく分からない…と感じていませんか?
GoogleのSGE(AI概要)が登場してから、検索の仕組みが大きく変わろうとしています。これまでのSEO対策だけでは不十分で、何か新しい始め方をしないといけないのでは、と焦っている方もいるかもしれません。
この記事では、AI検索時代に必須となる「LLMO対策のやり方」について、その基本的な考え方から、E-E-A-Tの強化、構造化データの実装といった具体的な方法まで、Web制作のプロの視点で分かりやすく解説していきます。
- LLMOとは何か、SGEとどう違うかが分かる
- 従来のSEO対策が無駄にならない理由
- AIに引用されやすいコンテンツの作り方
- 今すぐ始められるテクニカルな最適化手法
【基礎知識】概念の理解とSEOとの決定的な違い

まずは基本の「き」から。LLMOが何を指していて、従来のSEOと何が決定的に違うのか。ここをしっかり押さえておかないと、対策の方向性を見誤ってしまうかも。まずは基本概念を整理していきましょう。
LLMOとは何か?AI検索時代の新常識

LLMOは、「Large Language Model Optimization」の略で、日本語にすると「大規模言語モデル最適化」となります。
なんだか難しそうですが、要はChatGPTやGoogleのSGE(AI概要)といった「AI」に対して、あなたのサイトの情報を「信頼できる情報源」として認識させ、AIの回答で引用・参照してもらうための対策のことです。
従来のSEO(検索エンジン最適化)が、Googleの検索ロボット(クローラー)を主な対象として「検索順位を上げる」ことを目指していたのに対し、LLMOは「AI(大規模言語モデル)」そのものを対象にする、まったく新しい最適化戦略なんですね。
LLM(大規模言語モデル)の仕組みとLLMO
LLMというのは、インターネット上の膨大なテキストデータを学習して、「次にくる単語」を予測するように訓練されたAIのことです。この学習(トレーニング)によって、AIは人間のように自然な文章を生成したり、質問に答えたりできるようになります。
ここがポイントなんですが、AIが回答を生成する際、その「元ネタ」となる情報が必要です。その元ネタとして、AIが学習したデータや、リアルタイムでWebから収集した情報を「再構成」して、回答を作り出します。
LLMOとは、このAIによる「抽出・再構成」のプロセスにおいて、自社の情報を優先的に、かつ正確に選ばせるための戦略的アプローチなんです。
従来のSEOが「検索結果」という棚の良い場所(上位)を取りに行く戦略だったとすれば、LLMOは「AI」という優秀な店員さんに「この商品(自社情報)は信頼できるし最高ですよ」と覚えてもらい、お客様(ユーザー)への接客トーク(AIの回答)の中で紹介してもらう戦略、みたいなイメージかなと思います。
検索体験の構造的シフト
これまでのWebマーケティングは、ユーザーが「検索」し、表示された「リンク」をクリックし、「Webサイト」を訪問する、という流れが前提でした。
しかし、AI検索の登場によって、この流れは根本から変わる可能性があります。
ユーザーはAIと「対話」するようになり、AIが要約した「回答」を得るだけで満足し、個別のサイトを訪問しないかもしれません(これが「ゼロクリック検索」と呼ばれるものです)。
この「検索から対話へ」という構造的なシフトの中で、従来の「クリック(トラフィック)獲得」だけを追い求めていると、時代の変化に取り残されてしまうリスクがあるんです。
LLMOは、この新しい対話型の検索体験の中で、いかにして自社の価値をユーザーに届け、認知してもらうか、という新しい時代のWeb戦略の核心部分なんですね。
Googleの「SGE」とLLMOの関係性

LLMO対策を考える上で、今最も身近で、かつ影響力が大きい具体的な対象が、Googleの「SGE (Search Generative Experience)」、いわゆる「AIによる概要(AI Overview)」です。
SGEは、従来のGoogle検索結果ページ(SERPs)の一番上に、AIが生成した回答の要約を表示する新機能です。あなたもPCやスマホで、検索結果の上にAIの回答が表示されているのを目にしたことがあるかもしれません。
このSGEの回答は、多くの場合、Web上の複数のサイト情報をソース(情報源)としています。そして、その情報源となったWebサイトへのリンクが、回答の右側や下部に「参照リンク」としてカード形式で表示されますよね。
LLMOの当面の目標、特にGoogle検索における目標は、あのSGEの「AIによる概要」の回答文中に、自社のコンテンツ、ブランド名、またはサービス名を引用・言及させること、そして、その情報源である「参照リンクのカードに、いかにして自社サイトを選ばせるか」、という点にあるんです。
SGEの回答が生成されるプロセス(推測)
SGEがどのように回答を生成しているか、その詳細なアルゴリズムは公開されていませんが、一般的には以下のように推測されています。
- ユーザーが検索クエリ(質問)を入力します。
- Googleはまず、従来の検索アルゴリズム(SEOの評価)を使って、そのクエリに関連性が高く、信頼できるWebページをランク付けします。
- AI(LLM)は、それらの上位表示された信頼できるページ群から、ユーザーの質問に対する答えとなる部分を抽出し、要約・再構成します。
- その結果を「AIによる概要」として提示し、情報源となったページを「参照リンク」として付記します。
このプロセスで重要なのは、ステップ2です。AIが参照する元ネタは、Web上にある全てのページではなく、「まずSEOで高く評価されている信頼できるページ」が優先的に選ばれている可能性が非常に高い、という点です。ここが、後述する「SEO対策は不要になるのか?」という疑問への答えにも繋がってきます。
SGE以外のLLMO対象
もちろん、LLMOの対象はGoogleのSGEだけではありません。
- ChatGPT (OpenAI): Webブラウジング機能を使ってリアルタイムの情報を参照・引用することがあります。
- Perplexity AI: 回答と同時に、非常に明確に「情報源(Sources)」を提示することを特徴とするAI検索エンジンです。
- Microsoft Copilot (Bing): Bing検索と統合されており、検索結果に基づいた回答と参照元を提示します。
これらのAIも、Web上のどの情報を「信頼できる」と判断し、引用するかの基準を持っています。SGE(Google)対策としてE-E-A-Tを高め、一次情報を提供することは、結果として他のAIプラットフォームからも「信頼できる情報源」として認識されやすくなる可能性が高いと私は考えています。根本的な「良質な情報とは何か」という評価軸は、どのAIでも共通する部分が多いはずですからね。
「目的」と「評価軸」の違いを比較

ここで、「じゃあ、LLMOとSEOって結局、何がどう違うの?」という疑問が改めて出てきますよね。これは非常に重要なポイントです。両者の違いを理解することは、今後の戦略を立てる上で不可欠です。
LLMOとSEOは、その目的、対象、手法、そして評価基準において決定的に異なります。まずは、前回もお見せしたこの比較表をもう一度見てみましょう。
LLMOとSEOの比較表
| 比較項目 | SEO (検索エンジン最適化) | LLMO (大規模言語モデル最適化) |
|---|---|---|
| 目的 | 検索順位を上げ、クリック(流入)を獲得する | AIの回答に引用・言及され、 ブランド認知や新たな接点を創出する |
| 対象 | 検索エンジン(クローラー) | 生成AI(LLM)、Google SGEなど |
| 主な手法 | キーワード最適化、被リンク獲得、技術的SEO | E-E-A-T強化、一次情報の提供、 Q&A形式、構造化データ |
| 評価基準 | 検索順位、クリック数、CV数 | AIによる引用・言及数、ブランド指名検索数 |
最大の分岐点:「目的」と「成果地点」
この表で一番大きな違いは「目的」です。ここ、めちゃくちゃ大事です。
従来のSEOの目的は、「検索順位を上げて、自社サイトへクリック(トラフィック)してもらうこと」でした。成果地点は「検索結果ページ(SERPs)での上位表示とクリック」です。
一方、LLMOの目的は、「AIの回答文脈で引用・言及されること」そのものになります。成果地点は「AIの回答(SGE概要など)の文脈内」です。
なぜこの違いが重要かというと、AIが検索結果の最上部で完璧な要約(答え)を提示してしまうと、ユーザーはわざわざ個別のサイトをクリックすることなく、検索行動を完了させてしまう可能性が高まるからです。これが「ゼロクリック検索」と呼ばれる現象です。
ゼロクリック検索時代の新たな戦い方
SGEやAIチャットボットは、このゼロクリック検索を強烈に加速させると言われています。従来のSEOのみに依存し、「クリックされてナンボ」という戦略だけでは、AIが完璧な回答を提示するようになった時、これまで獲得できていたはずのサイトへのトラフィックが激減する、という重大なリスクに直面します。
「え、じゃあどうすれば…」となりますよね。
ここでLLMOの出番です。LLMO対策は、この「ゼロクリック」という不可避な環境下で、たとえクリックされなくても、AIの回答という信頼性の高いコンテキストの中で「自社ブランド名」や「独自のサービス名」、「独自のノウハウ」を戦略的に言及させることで、ユーザーの認知を獲得するための「必須の防衛戦略」であり、かつ「新たな攻撃戦略」でもあるんです。
例えば、ユーザーが「おすすめの〇〇は?」とAIに聞いた時、AIの回答が「A社、B社、そしてC社(あなたの会社)の製品が人気です。特にC社は△△という独自の強みがあります。」と、あなたの会社に言及してくれるかどうか。これがLLMOの戦いです。
クリックは発生しなくても、Googleという信頼できるプラットフォーム上のAIが「C社は△△が強み」と言及すること自体のブランド認知効果は、計り知れない価値があると思いませんか?
キーワード最適化の限界
もう一つの大きな違いは「手法」です。従来のSEOでは「キーワードをいかに適切に配置するか」というキーワード最適化が非常に重要でした。
しかし、LLMOの対象であるAI(LLM)は、キーワードの有無だけでなく、「文脈」や「意味」を深く理解します。AIにとって、単にキーワードが散りばめられているだけの薄っぺらいコンテンツは、引用する価値がありません。
それよりも、E-E-A-Tが担保された(信頼できる)上で、AIがまだ学習していないような「一次情報」や「独自の分析」が、AIにとっての「新しい知識」として引用価値が高くなるんです。
このように、LLMOはSEOとは似て非なる、まったく新しいゲームルールの上で行われる最適化戦略だということが、なんとなく掴めてきたでしょうか。
SEOは不要?むしろ「重要度が増す」理由
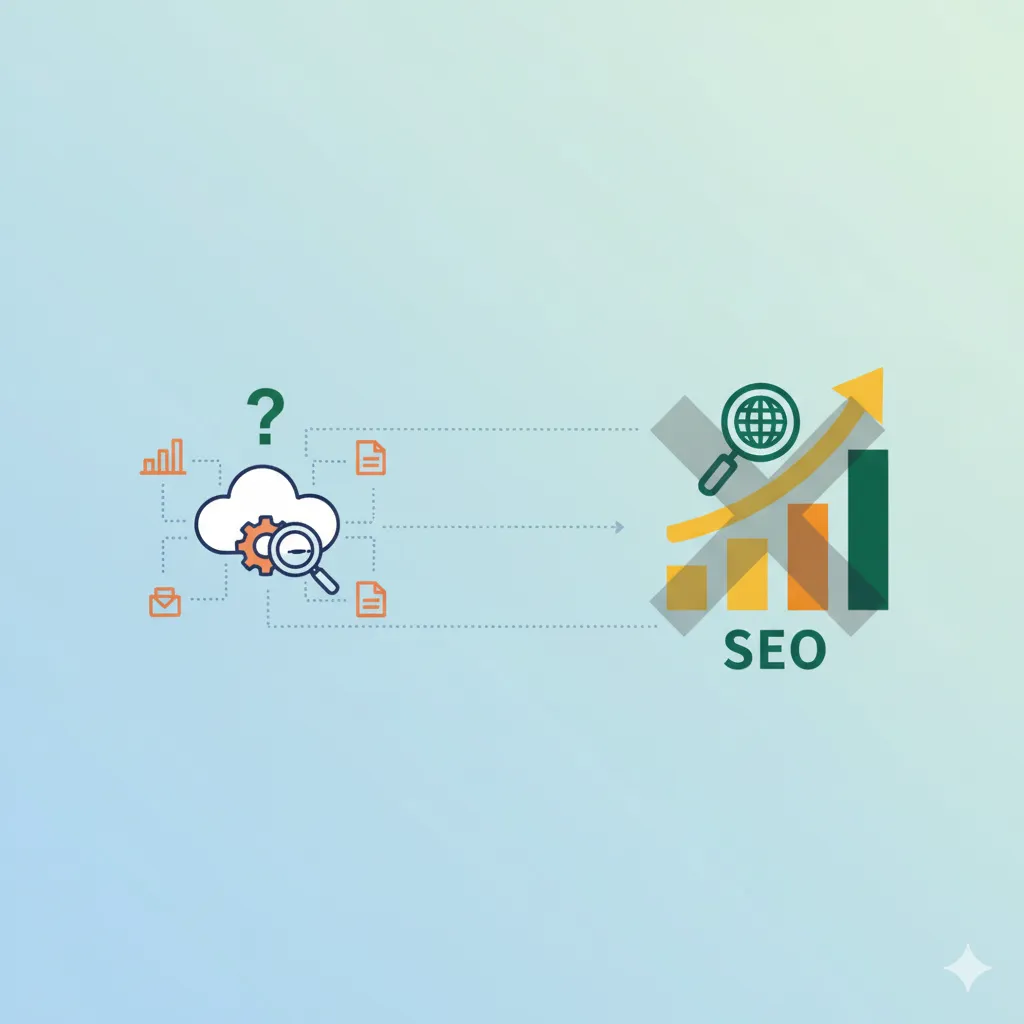
LLMOという新しい概念が出てくると、「じゃあ、もうSEOはオワコン(終わったコンテンツ)なの?」「今までのSEO対策は全部ムダになるの?」と不安になるかもしれません。
ですが、ハッキリ言います。それは明確な間違いです。
結論から言うと、SEO対策は不要になるどころか、LLMO対策を成功させるための「土台」として、その重要性はむしろ以前よりも増していると私は考えています。
AIが信頼性を判断する「初期シグナル」
「あれ? さっきLLMOとSEOは違うって言ったじゃない」と思うかもですが、両者は「対立」するものではなく、「相互に補完し合う」関係なんです。
SGEの概要(AI Overview)の仕組みでも触れましたが、AIは、Web上の膨大な情報から「信頼できる」情報源を選んで回答を生成します。では、AIは何をもって「信頼できる」と判断するでしょうか?
AIが、Web上の何十億というページを一瞬ですべて精査し、どれが信頼できるかゼロから判断するのは非効率ですよね。
そこでAIは、まず「初期フィルター」として、「従来のGoogle検索アルゴリズム(SEO)で、すでに関連性が高く、品質が高いと評価されている(=検索上位にいる)サイト」を優先的に参照している可能性が非常に高いんです。
考えてみれば当然で、Googleが長年かけて培ってきたSEOの評価軸(被リンク、コンテンツの品質、E-E-A-Tなど)は、AIにとっても「この記事が信頼できるかどうか」を判断するための、強力な初期シグナルになるはずです。
実際、Ahrefs(エイチレフス)という有名なSEO分析ツールが実施した調査によれば、GoogleのAI概要(SGE)で引用されるWebサイトの約76%が、その検索クエリにおけるSEOの上位10位以内にランクインしているページであった、と報告されています。
これは、AIが引用元を選定する際、まずSEOで高く評価されているコンテンツを、信頼性の高い情報源として優先的に参照していることを強く示唆していますよね。
SEOとLLMOの相乗効果
つまり、こういうことです。
- まず、SEO対策(E-E-A-Tの強化、良質なコンテンツ作成、技術的SEOなど)を徹底的に行い、検索順位という「信頼の土台」を築きます。
- AI(SGE)は、その「信頼の土台」の上にあるページ(=SEO上位ページ)を優先的に参照します。
- その上で、そのページがLLMO対策(AIが引用しやすい構造、Q&A形式、一次情報など)も満たしていれば、AIは喜んでその内容を回答に引用・言及します。
「LLMO対策のやり方」における真の第一歩は、対象領域において強力なSEO対策を継続・実施し、AIの「参照候補」として土俵に上がることなんです。
もしSEO対策をサボってしまい、検索順位が圏外(例えば50位とか)だったら、AIはそのページを「信頼できる情報源」として認識する以前に、そもそも「見つけて」すらもらえない可能性が高い、ということです。
だから、SEO対策は決して無駄にはなりません。むしろ、AI時代に選ばれるための「入場券」として、その重要性はさらに増しているんです。
E-E-A-T強化と一次情報

SEOがLLMOの「土台」である、という話をしました。その土台の中でも、特にLLMOと直結し、AIに「この情報源は最高に信頼できる!」と思わせるために最も重要なのが「E-E-A-T」です。
E-E-A-Tは、Googleがコンテンツの品質を評価するための最重要ガイドラインで、以下の4つの頭文字をとったものです。
- E – Experience(経験): 実際に製品を使った、サービスを利用した、その場所を訪れた、といった実体験に基づいているか。
- E – Expertise(専門性): コンテンツの作成者が、そのトピックに関する専門家であるか。
- A – Authoritativeness(権威性): コンテンツの作成者やWebサイト自体が、その分野の権威として広く認識されているか。
- T – Trustworthiness(信頼性): 情報が正確で、誠実であり、サイトが安全であるなど、全体として信頼できるか。
AI(特にGoogleのSGE)は、誤情報や不確かな情報を回答として生成してしまうこと(ハルシネーション=幻覚)を極端に避けるように設計されています。そのため、回答の「元ネタ」として参照する情報源が、このE-E-A-Tをどれだけ満たしているかを、従来のSEO以上に厳しくチェックしていると考えられます。
では、LLMO対策としてE-E-A-Tを強化するとは、具体的に何をすればいいんでしょうか?
E – Experience (経験): AIには「体験」ができない
LLMは膨大なテキストデータを学習していますが、AI自身が「製品を使う」ことや「サービスを体験する」ことはできません。ここが最大の差別化ポイントです。
「実際に使ってみた」「やってみた」系のレビュー記事、サービス導入のビフォーアフター、現場での失敗談と改善策など、あなた(あなたの会社)にしか書けない「実体験」に基づくコンテンツは、AIにとって非常に価値の高い情報源(一次情報)となります。
表面的なスペックの羅列ではなく、使ったからこそ分かる「使い心地」「メリット」「デメリット」を具体的に記述することが、E-E-A-Tの「経験」を示すことに繋がります。
E – Expertise (専門性) & A – Authoritativeness (権威性)
「誰が」その情報を発信しているかは、信頼性を判断する上で極めて重要です。
著者情報の明記(専門性): 記事ごとに、その分野の専門家である著者情報(詳細なプロフィール、過去の実績、SNSリンク、保有資格など)や、監修者情報を明確に記載します。「この記事は、この分野で10年の経験を持つ専門家が書いています」とAIに伝えるわけです。
運営者情報の開示(権威性): サイトの運営者情報(会社概要)を詳細に開示し、その組織が当該分野の権威であることを示します(これは後の「エンティティ強化」にも繋がります)。
T – Trustworthiness (信頼性)
サイト全体の信頼性です。常時SSL化(https://)のような技術的な安全性はもちろん、情報が正確であること、最新であること、公的機関やメーカー公式サイトなど「信頼できる情報」を引用・参照していること(そしてその出典を明記すること)が重要です。
最強の武器:「一次情報」と「独自データ」
そして、E-E-A-Tを担保した上で、AIに「引用する価値がある」と判断させる最強の差別化要因が、「一次情報」と「独自データ」です。
AIの得意分野(二次情報)で勝負しない
Web上に溢れている「他のサイトの情報をまとめただけ」のコンテンツ、いわゆる「二次情報」は、LLMにとって参照する価値が非常に低くなります。
なぜなら、その程度の要約やまとめは、AI自身が最も得意とする作業だからです。AIは、AIでも作れるようなコンテンツを、わざわざ引用元として選びません。
AIに「おっ、これは新しい情報だ」「これはウチ(AI)では生成できない価値あるデータだ」と思わせる必要があります。それこそが「一次情報」です。
AIに引用されやすい「一次情報」の例
- 自社で独自に実施したアンケート調査の結果や、市場分析レポート(例:「自社顧客1000人に聞いた、〇〇の悩みランキング」)
- 独自の顧客インタビューに基づく詳細な導入事例や成功事例(数字や具体的なエピソードを含む)
- 特定の業界課題に対する、社内の専門家による独自の考察や分析、未来予測
- 建設会社であれば実際の詳細な施工例、製造業であれば自社での研究開発データ
LLMは「知識の再構成」によって回答を作ります。LLMOにおけるコンテンツ戦略の本質とは、AIがその「再構成」を行うための、他にはないユニークで高品質な「素材(=一次情報)」を提供することにあります。AIにとっての「新情報」こそが、引用元として選ばれる最大のフックとなるのです。
AIに選ばれるための「具体的な実装テクニック」
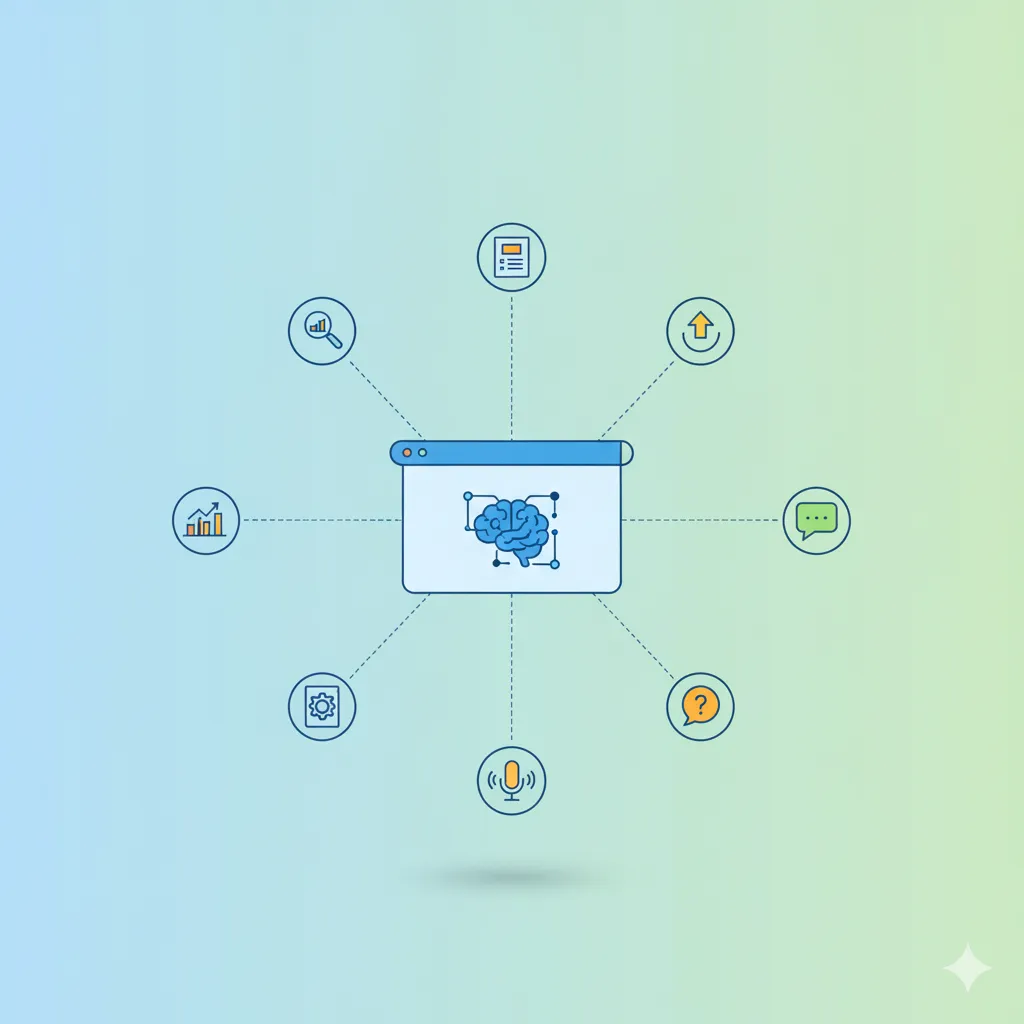
基本が分かったところで、ここからは「じゃあ具体的にどうすればいいの?」という実践的なテクニックに入っていきましょう。AIに「このサイトの情報は分かりやすくて信頼できる!」と思ってもらうための具体的な「やり方」です。私たちWeb制作者の腕の見せ所でもありますよ。
AIが理解しやすい「論理構造」の作り方

どれほど優れた一次情報であっても、AIが「扱いにくい」「意味が分かりにくい」形式で書かれていては引用されません。AIは(今のところ)人間のように「行間を読む」のはまだ苦手です。
だからこそ、AI(LLM)という「機械」が、そのコンテンツの「意味」や「文脈」を誤解なく、正しく理解するのを助ける「構造」で情報を提供してあげることが、めちゃくちゃ重要になってきます。
これは、私たちWeb制作者が昔から重視してきた「セマンティックHTML(HTMLタグをその意味論に従って正しく使うこと)」の考え方そのものなんです。
結論ファースト(PREP法)とAIの予測
AIが文章を処理するとき、文脈を予測しながら読み進めます。冗長な前置きや曖昧な表現が続くと、AIは「この記事の要点は何だ?」と混乱してしまいます。
常に結論(Point)から先に述べ、次にその理由(Reason)、具体例(Example)、そして最後に再び結論(Point)でまとめる「PREP法」を意識しましょう。
これは人間にとって分かりやすいだけでなく、AIにとっても「このブロックの主張はこれだな」と要点を抽出しやすい、非常にAIフレンドリーな文章構成です。
リスト・表の活用(情報の「構造化」)
伝えるべき情報が多い場合、文章でダラダラと羅列するのは最悪です。人間も読み飛ばしますし、AIも「どこからどこまでが一つの情報セットなのか」を理解するのが難しくなります。
箇条書き(<ul>, <ol>)や表(<table>)を積極的に使いましょう。
これらのHTMLタグで情報を囲むことは、AIに対して「これらは同レベルの項目(リスト)ですよ」「これは行と列で整理されたデータ(表)ですよ」と、情報の「構造」を明示的に伝えることになります。AIは構造化されたデータが大好きです。これにより、情報が視覚的・論理的に整理され、AIが論理構造を解析しやすくなり、引用の精度が上がります。
見出し(Hタグ)の論理階層
これはWeb制作の基本中の基本ですが、LLMOにおいてその重要性はさらに高まっています。
<h1>: 記事の(大)タイトル(1ページに1つだけ)<h2>: 記事の主要なセクション(大見出し)<h3>: 各セクション内のトピック(中見出し)<h4>: 各トピック内の詳細(小見出し)
この<h1> → <h2> → <h3> → <h4> という階層構造を論理的に正しく保つこと。これが崩れている(例: <h2> の次にいきなり <h4> が来る)サイトが意外と多いんですが、これはAIに対して「この記事の目次(構造)はぐちゃぐちゃですよ」と宣言しているようなものです。
見出し階層を正しく使うことは、AIに「この記事の全体像(目次)」を正確に渡すことであり、AIが記事の文脈を理解する上で強力な手助けになります。
質問型見出し(クエリファンアウト対応)
ここ、特に意識したいテクニックです。
AI検索の内部では、「クエリファンアウト (Query Fan-out)」と呼ばれる高度なメカニズムが働いていると考えられています。
これは、AIがユーザーから受け取った1つの抽象的な質問(例:「LLMOとは?」)を、AIが内部で複数の具体的なサブクエリ(「LLMOの定義は?」「LLMOはなぜ必要なのか?」「LLMOの施策には何がある?」)に自動で分解(Fan-out)し、それらのサブクエリを並行処理して得られた情報を統合し、最終的な回答を生成する仕組みです。
このAIの内部動作に「先回り」するコンテンツ設計こそが、最強のLLMO対策の一つとなります。
「質問型見出し」でAIのサブクエリに応える
(従来の書き方)
<h2>LLMOの概要</h2>
<h2>LLMOの施策</h2>
(LLMO対策後の書き方)
<h2>LLMOとは何か?</h2>
<h2>LLMO対策の具体的な進め方は?</h2>
このように見出しを「質問型」にし、その直下にその「回答」となる本文を簡潔に配置します。この構造を採用することで、AIが内部で生成したサブクエリと、あなたのコンテンツの見出しテキストが一致する確率が高まります。
AIは「この見出しは質問であり、その直下の本文は回答である」という文脈を正確に把握できるようになり、そのブロックを回答の一部として引用する確率が劇的に向上するのです。
FAQセクションを「戦略的」に配置する

先ほどの「質問型見出し」のアプローチと密接に関連して、記事の最後やトピックのまとめとして「Q&A(よくある質問)」セクションを設けることは、非常に強力なLLMO対策になります。
なぜFAQがそんなに強力なのか? それは、ChatGPTのような対話型AIは、もともと「質問」に対して「回答」を生成するのが得意であり、その学習データ(教師データ)の多くが「Q&A形式」で構成されているからです。
AIは「Q&A」という形式に非常によく慣れ親しんでいるんです。
そのため、「〇〇とは?」「〇〇のやり方は?」といった具体的な「問い(Q)」と、それに対する明確な「答え(A)」がセットになったFAQコンテンツは、AIにとって回答を生成するための直接的な「部品」として、この上なく利用価値が高いのです。
AIは、ユーザーからの質問に似た「問い(Q)」をあなたのFAQセクションで見つけると、「お、ここにピッタリの答え(A)があるぞ!」と判断し、その「答え(A)」の部分を回答に引用しやすくなります。
効果的なFAQの「作り方」
じゃあ、どんなFAQを作ればいいんでしょうか?
1. ユーザーインテントの先回り(Qの抽出)
やみくもにQ&Aを作っても意味がありません。ユーザーが「実際に」疑問に思うであろうことを「問い(Q)」にする必要があります。
ネタ探しの簡単な方法は、Google検索であなたの記事のメイントピック(例:「LLMO対策」)と検索した時に表示される「他の人はこちらも質問」(People Also Ask)や、検索窓のサジェストキーワード(例:「LLMO対策 やり方」「LLMO対策 SEO 違い」)を参考にすることです。これらは、ユーザーが実際に検索している「生きた疑問」そのものです。
2. 回答(A)の書き方
「問い(Q)」に対する「答え(A)」は、「簡潔に、かつ網羅的に」書くのがコツです。まず結論(答え)をズバリと書き、必要であれば補足説明を加えます。専門用語を避け、AIがそのまま引用しても問題ないくらい、平易で完成された文章を心がけましょう。
3. 設置場所の最適化(マイクロFAQ)
記事の末尾にまとめてFAQを設置するのも良いですが、私のおすすめは、各<h2>や<h3>のセクションの終わりに、そのセクションに関連するQ&Aを1〜2個設置する「マイクロFAQ」という手法です。
これにより、文脈がより明確になり、AIも「このセクションのまとめのQ&Aだな」と理解しやすくなります。
そして、このFAQセクションを作ったら、次の「構造化データ」と組み合わせることで、その効果を何倍にも高めることができます。
意味を伝える「構造化データ」の実装
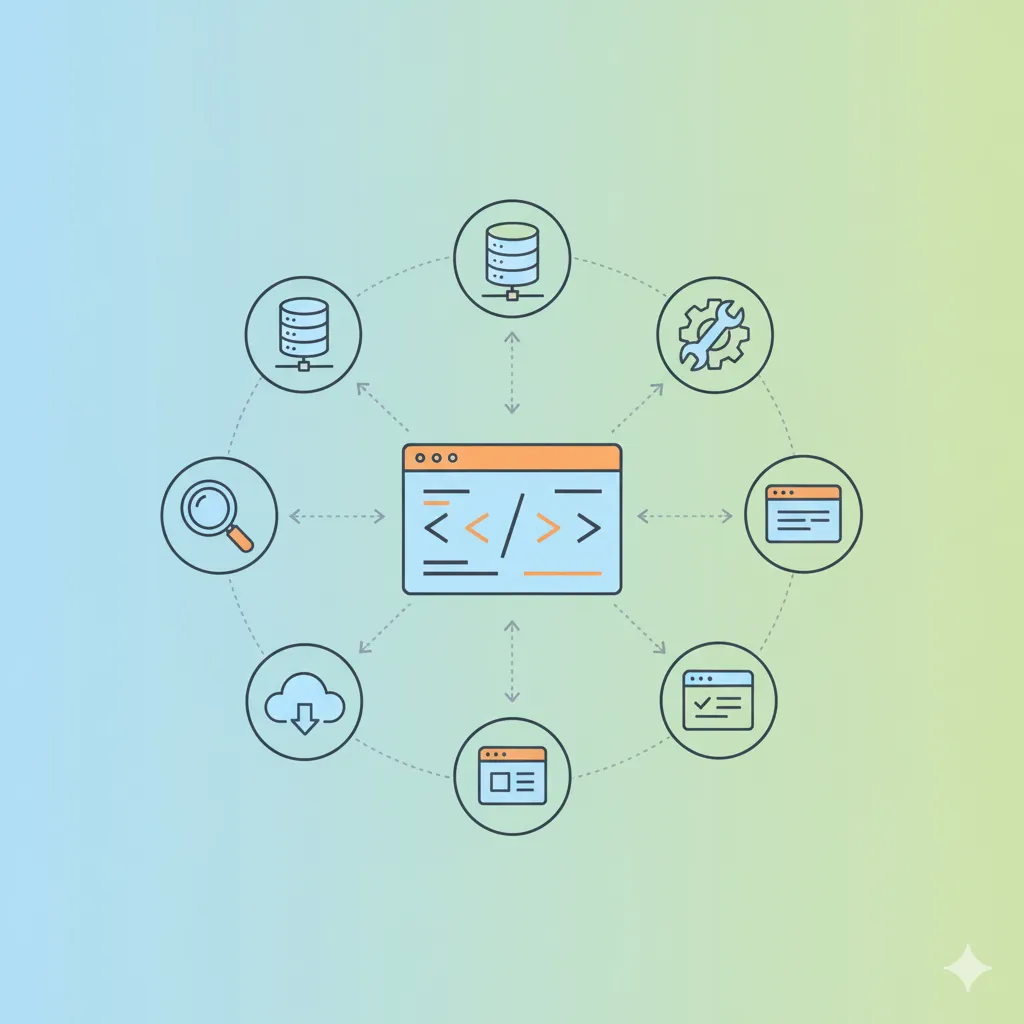
ここからは少し専門的になりますが、私たちWeb制作者・マークアップエンジニアの腕の見せ所であり、LLMO対策の「やり方」において非常に強力なテクニック、「構造化データ」の実装について解説します。
優れたコンテンツを作り、AIが引用しやすい構造(質問型見出しやFAQ)にした。素晴らしいです。でも、あと一押し、AIに「確実に」その意味を伝えるための技術的なダメ押しがあります。それが構造化データです。
構造化データとは? AIに「意味」を教える技術
構造化データとは、簡単に言えば、Webページ上の情報が「何であるか」を、AIや検索エンジンが理解できる共通の言葉(ルール)で明示的にタグ付けすることです。
例えば、人間の目には「Q: LLMOとは?」と「A: 大規模言語モデル最適化のことです。」というテキストは、これが「質問と回答のペア」であると文脈から分かります。しかし、AIはこれを単なる「テキストの羅列」として誤解する可能性がゼロではありません。
そこで、構造化データ(FAQPageスキーマというルール)を使って、HTMLの裏側(通常は<head>内や<body>内にJSON-LD形式で記述)で、
「(ここからが質問テキストです)Q: LLMOとは?(ここまでが質問です)」
「(ここからが回答テキストです)A: 大規模言語モデル最適化のことです。(ここまでが回答です)」
と、AIに対して「このテキストは『質問』であり、このテキストは『その回答』ですよ」と、意味を正確に(機械的に)伝えてあげる技術です。
LLMOで最優先に実装すべきスキーマ
構造化データのルール(スキーマ)は無数にありますが、LLMO対策、特にE-E-A-Tとエンティティ強化の観点から、以下のスキーマは最優先で実装を検討すべきです。
FAQPage(FAQページ) 前述のQ&Aセクションには、これを必ず実装します。SGE対策(LLMO対策)において最も相性が良いとされています。AIに「ここぞ」というQ&Aをピンポイントで教えることができます。Organization(組織) /LocalBusiness(ローカルビジネス) 会社概要(About Us)ページに実装します。企業の正式名称、住所、電話番号(NAP情報)、ロゴ、設立日、SNSリンクなどをAIに明示的に伝えます。E-E-A-Tの「権威性」と「信頼性」、そして「エンティティ強化」の核となります。Person(人物) /Author(著者) 著者(監修者)紹介ページや、記事自体に「この記事を書いたのはこの専門家です」と明示するために使います。E-E-A-Tの「専門性」をAIに伝える強力なシグナルです。Article(記事) /BlogPosting(ブログ投稿) 記事のタイトル、公開日、最終更新日、著者、発行者(Organization)といった基本情報をAIに正確に伝えます。情報の「鮮度」や「発行元」を伝える上で重要です。
これらの構造化データを正しく実装することで、AIはあなたのコンテンツの文脈(これは会社概要、これはFAQ、これを書いたのはこの専門家)をより深く、正しく理解できるようになり、回答生成時の引用の精度と確率が向上します。
Googleは構造化データに関する詳細なガイドラインを公開しています。私たち制作者は、こういった一次情報源を常にチェックしながら、最新の正しい実装を心がけています。(出典: Google検索セントラル『SEO スターター ガイド』)
実装ミスは逆効果! 検証を忘れずに
構造化データは強力ですが、記述方法を間違えたり、ガイドラインに違反する使い方(例:見えていない内容を記述する)をしたりすると、ペナルティを受けたり、AIに無視されたりする逆効果も生みます。
実装後は、必ずGoogleの「リッチリザルトテスト」ツールなどを使って、正しく認識されているかを検証する作業が不可欠です。ここは専門的な知識が必要なので、自信がない場合は私たちのような専門家に相談するのが一番早いかもしれませんね。
新規格「llms.txt」の役割と記述例

もう一つ、LLMO対策に関連する新しいテクニカルなトピックとして「llms.txt」を紹介します。これは、最近出てきた新しい「お作法」のようなものです。
llms.txtとは、Webサイトの運営者が、AIクローラー(AIの学習用データを収集するボット)に対して、サイト内のどのコンテンツをAIの学習や回答生成に利用してよいか(あるいは禁止するか)を明示的に指示するためのファイルです。
あなたのサイトのコンテンツが、知らないうちにAIの学習データとして無断で利用されるのを防いだり、逆に「この情報はAIに積極的に引用してほしい!」と意思表示したりするために使います。
robots.txtとの違いと関係性
Web制作に詳しい方なら「それってrobots.txtと何が違うの?」と思いますよね。いい質問です。
robots.txt(従来のファイル):- 対象: 主に検索エンジンのクローラー(例: Googlebot)。
- 目的: 主に「インデックス(検索結果への表示)」を制御する。
llms.txt(新しいファイル):- 対象: 主にAI(LLM)のクローラー(例: GPTBot, Google-Extended)。
- 目的: 主に「AIの学習データとしての利用」や「回答への引用」を制御する。
ここがややこしいんですが、AIクローラーの中には、まずrobots.txtを見て、そこに自分(AIクローラー)への指示がなければ、次にllms.txtを見に行く…という動きをするものがある(あるいは、そういう標準化が進められている)んです。
ですから、robots.txtでAIクローラー(例: User-agent: Google-Extended)をうっかりブロック(Disallow: /)していないかを確認することも、LLMO対策の隠れた第一歩になります。
llms.txtの具体的な記述例(やり方)
llms.txtは、robots.txtと同様に、Webサイトのルートディレクトリ(例: https://example.com/llms.txt)に設置します。その記述方法はrobots.txtの構文と非常に類似しています。
llms.txtの簡単な記述例
# すべてのAIクローラーを対象 User-Agent: * Disallow: /internal/ Disallow: /private-content/
社内向け情報や機密情報はAIの学習・引用を禁止
Allow: /faq/ Allow: /product-specs/ Allow: /blog/
FAQ、製品仕様、ブログ記事は積極的に学習・引用してOK
特定のAIクローラーだけを制御することも可能
User-Agent: GPTBot Disallow: /
OpenAIのGPTBotには一切学習させない(例)
User-Agent: Google-Extended Allow: /
GoogleのAIにはすべて許可(例)
LLMOにおける戦略的ジレンマ
llms.txtの導入には、戦略的なジレンマが伴います。それは、「AIによる知的財産(IP)の保護」と「LLMO(AIによる引用促進)」という、相反する目的の板挟みになる可能性があるためです。
一部のニュース発行社などは、自社コンテンツがAIの学習データとして無断で利用されることを防ぐため、llms.txtを用いてAIクローラーのアクセスを全面的にブロック(例: User-Agent: * Disallow: /)する動きを見せています。
LLMOを目指すなら、ブロックは悪手
しかし、本記事の主題である「LLMO対策(AIに引用されること)」を目指す企業にとって、AIクローラーを一方的にブロックすることは戦略的な誤りとなります。
AIがあなたのコンテンツを読み込めなければ、当然ながらAIの学習データにもならず、SGEの回答に引用もされようがないからです。
したがって、LLMOにおけるllms.txtの正しい「やり方」とは、DisallowでAIを拒否することではなく、むしろAllowを戦略的に使いこなし、AIに引用してほしい「FAQページ」や「製品情報」「ブログ記事」などの重要なコンテンツ群へとAIクローラーを積極的に誘導することにあるんです。
現時点ではこのllms.txtの標準化はまだ道半ばであり、各AI(OpenAI, Google, Anthropicなど)の対応も完全には統一されていません。しかし、今後AIクローラーに対するサイト運営者の意思表示として、このファイルの重要性は増していくと考えられます。
エンティティ強化と権威性
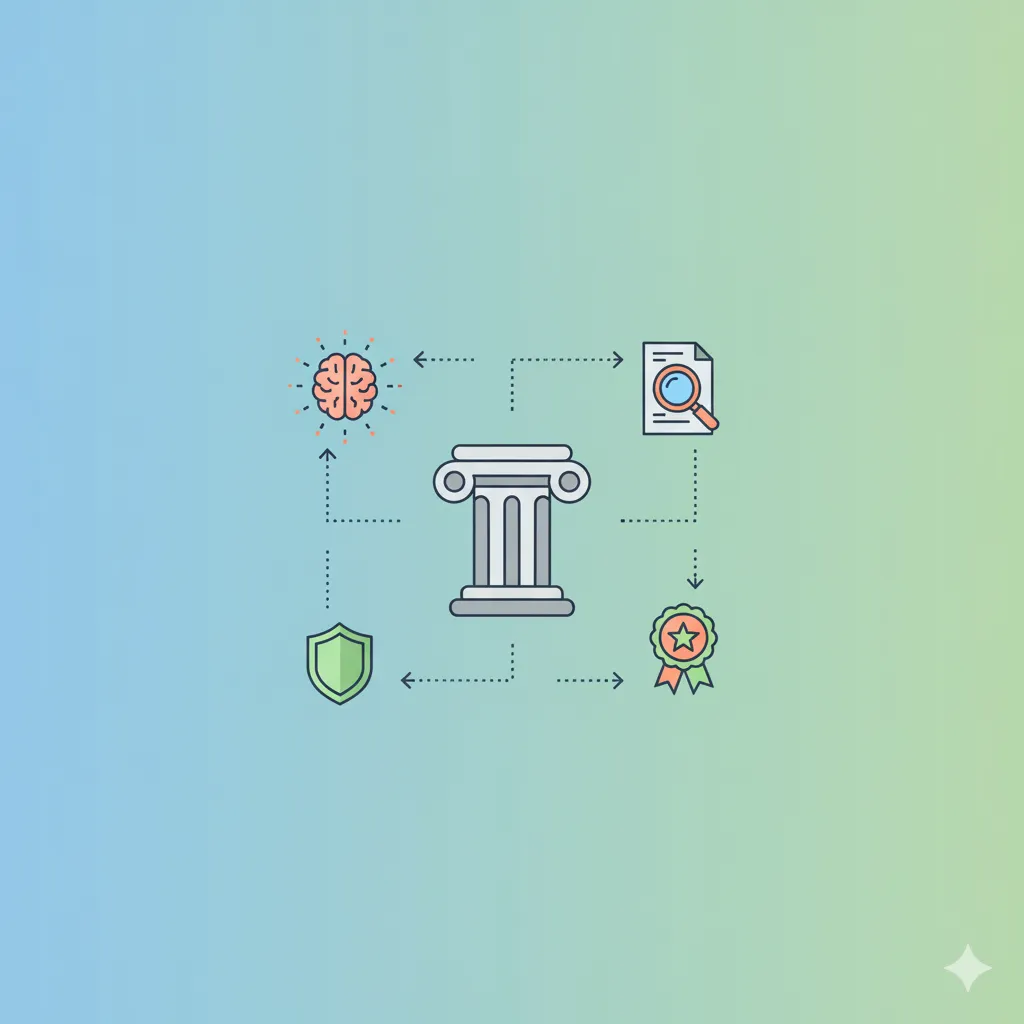
AIは、サイトが自ら「私はこの記事の専門家だ!」と主張するだけでは、それを鵜呑みにしません。AIがあなたの会社やあなた自身を「そのトピックにおける権威である」と客観的に認識するためには、サイトの内外からの「証拠」が必要です。
これが「エンティティ」と「権威性」の強化です。
エンティティとは、AIが文脈から認識する「実体(概念、モノ、場所、人物、企業など)」のことです。例えば、「hakubi code」や「てらだ」というのがエンティティです。
LLMOにおける重要な活動の一つは、自社の「エンティティ(例: hakubi code)」と、専門とする「トピック(例: Web制作, LLMO対策)」を、AIの知識ベース(ナレッジグラフ)の中で強固に紐づけることなんです。
サイト内部で完結するエンティティ構築
まずは、サイト内部で「私たちは何者なのか」をAIに正確に伝えることから始めます。これはE-E-A-Tの「専門性」「権威性」とも直結します。
1. 会社概要(About Us)ページの徹底的な充実化
これは企業のエンティティ情報を確立するための最重要ページです。単なる挨拶ではなく、以下の情報を「テキスト形式で」詳細に記述します。
- 企業の正式名称(登記上の名称)
- 住所(郵便番号から正確に)
- 電話番号(市外局番から)
- 設立年、沿革、ミッション、事業内容
- 受賞歴、所属団体、取引先実績
これらの情報(特に住所・電話番号)を、Googleビジネスプロフィールや他のWeb上の情報(NAP情報)と統一させることが重要です。これがAIに「この会社は実在し、信頼できる組織である」と判断させるための基礎情報となります。前述のOrganization構造化データと連動させるとなお良いですね。
2. 著者(Author)ページの作成と明記
著者個人のエンティティも同様に重要です。E-E-A-Tの「専門性」の塊です。
- 著者の氏名、顔写真
- 経歴、専門分野、保有資格
- 過去の実績、出版物、登壇歴
- 公式SNS(X, LinkedInなど)へのリンク
これらの情報を詳細に記した「著者紹介ページ」を作成し、各記事から「この記事を書いた人」としてリンクを貼ります。Person構造化データの実装も忘れずに。
サイト外部からの権威性シグナル
サイト内部で「私は専門家だ」と整えるだけでは不十分です。AIが本当に重視するのは、「第三者による客観的な評価」です。これが「権威性」のシグナルとなります。
権威性を高める「外部シグナル」の例
- 公的機関・教育機関からの被リンク: 省庁、自治体、大学(.go.jp, .ac.jp)など、信頼性が非常に高いドメインからの被リンクや言及。
- Wikipedia(ウィキペディア): AIが信頼性の高い情報源として参照する代表例です。自社、自社製品、あるいは自社の代表者に関するページが(中立的かつ正確な情報で)Wikipediaに掲載されることは、エンティティの権威性を証明する非常に強力なシグナルとなります。
- 権威ある業界メディア・ニュースサイトからの言及: あなたの専門分野における、誰もが知る業界専門メディアや、大手ニュースサイトから、「〇〇の専門家であるA社によれば…」といった形で、引用元としてリンクされたり、ブランド名が文脈の中で言及されたりすること(サイテーション)。
- プレスリリース (PR): PR TIMESなどの信頼できるプレスリリース配信サービスを経由し、新製品や「独自調査の結果(一次情報!)」を広く報道機関に通知します。これにより、上記のメディア露出(掲載)を図るきっかけになります。
LLMO時代において、こうした外部からの被リンクや(リンクなしの)ブランド言及(サイテーション)は、単なるSEOの「PageRank」を受け渡すためだけのものではありません。
それは、「AIが文脈を学習するための参照点」であり、かつ「そのエンティティの権威性を検証するための客観的な証拠」としての価値を持つのです。情報の信頼性を示す「引用」の重要性については、Webサイトにおける正しい引用の書き方を解説した記事も参考にしてみてください。
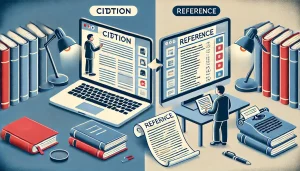
LLMOの効果測定とKPI

さて、ここまでLLMO対策の「やり方」をいろいろと解説してきましたが、LLMO対策を推進する上で直面する最大の課題が、「効果測定の難しさ」かもしれません。
SEOであれば、Google Search Consoleや順位チェックツールを使って、「検索順位が3位に上がった」「クリック数が20%増えた」「コンバージョン(CV)が5件発生した」といった明確な指標(KPI)が存在します。
しかしLLMOの場合、どうでしょう?
自社のコンテンツがAIの回答生成にどれだけ貢献したのか、あるいはSGEの回答文に何%影響を与えたのかを、直接的に計測する公式なツールや指標は、現時点では確立されていないんです。
これが、多くの企業がLLMO対策に踏み出せない大きな理由の一つになっています。「ROI(費用対効果)が測れない施策には、予算も工数も割けない」という判断になりがちなんですね。ここ、気になりますよね。
追跡すべき「間接的な指標(代替KPI)」
じゃあ、どうやって効果を測るのか? 「測れないからやらない」が一番のリスクであることは間違いありません。
私たちは、直接的な指標が存在しない以上、複数の「間接的な指標(代替KPI)」を組み合わせて定点観測し、施策の効果を推測・検証していく必要があると考えています。
LLMO対策の成果を測るために追跡すべき、主要な代替KPIは以下の通りです。
LLMO対策の主要KPI
- ブランド指名検索数の増加
これが最も重要な間接指標かもしれません。AIの回答(SGEなど)で自社のブランド名やサービス名が頻繁に言及されることで、ユーザーの認知度が高まります。その結果、AIの回答を見たユーザーが、後でそのブランド名を直接検索(例:「〇〇会社」「〇〇 サービス」)する行動が増加すると予測されます。 (確認方法: Google Search Console の「検索パフォーマンス」で、自社ブランド名を含むクエリの表示回数やクリック数の推移を監視) - AIサービスからのリファラー(参照元)流入
SGEの参照リンクや、Perplexity.aiなどのAIサービス経由で、実際にサイトに訪問(クリック)してくれたトラフィックを計測します。ゼロクリック検索が増えるとはいえ、ゼロになるわけではありません。AI経由の「質」の高い流入が増えているかを確認します。 (確認方法: GA4(Google Analytics 4)のレポートで、「参照元 / メディア」にAIサービス(例: perplexity.ai, t.co など)がないかを確認) - AI回答における言及・引用数のモニタリング
最も直接的な成果ですが、測定が難しい指標です。ターゲットとする主要なキーワード(例:「LLMO対策 やり方」)で、SGEやChatGPTで定期的に検索し、AIの回答や参照リンクに自社ブランドやコンテンツがどれくらいの頻度で、どのような文脈(好意的か、中立的か)で言及されているかを「手動で」定点観測します。 (確認方法: 現状は手動での確認が主だが、Ahrefsなど一部のSEOツールがSGEの順位追跡機能などを開発中)
「測定の難しさ」が「先行者利益」を生む
LLMOが「効果測定が難しい」という事実は、一見すると施策推進の大きな障壁(リスク)に見えます。
しかし、私は視点を変えれば、これこそが最大の「チャンス」であるとも言えます。
明確なROI(費用対効果)を短期的に提示しにくい施策は、多くの企業、特に予算執行に厳格な大企業において、承認されにくく、後回しにされがちです。
しかし、検索体験のAIへの移行は、不可逆的なトレンドです。
したがって、ROIが不明確な「今」この瞬間に、他社が明確な指標を求めて躊躇している間に、中長期的な視点に立って投資判断ができる企業のみが、E-E-A-Tの強化や一次情報の蓄積といった、時間のかかる「真似されにくい」資産を築き上げることができます。
この時間差こそが、数年後に圧倒的な「先行者利益」(=AIからの揺るぎない信頼)となって結実するのです。
結論:AIの先にある「ユーザー」を見据えよう
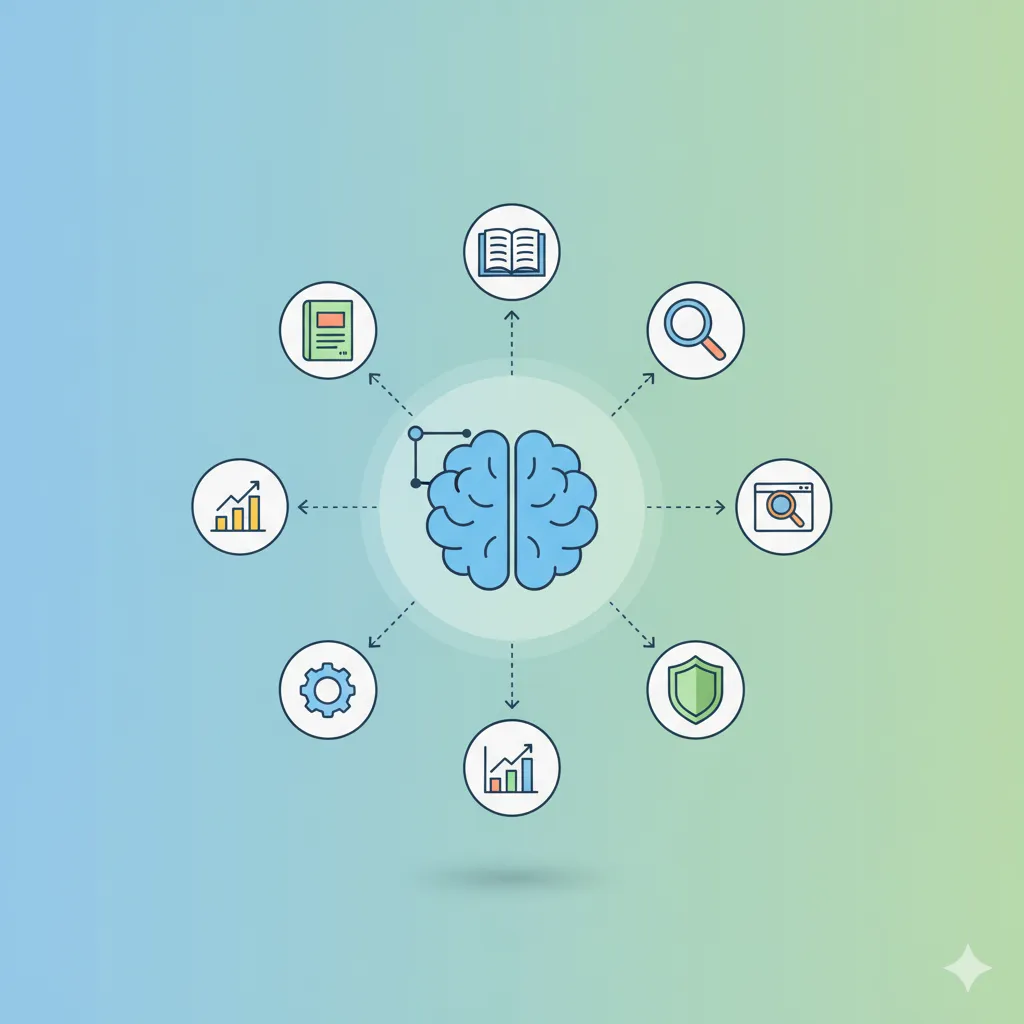
ここまで、LLMO対策の基本的な考え方から、E-E-A-Tの強化、一次情報の重要性、そしてAIが引用しやすいコンテンツ構造、構造化データ、llms.txtといった具体的な「やり方」を、かなり詳細に解説してきました。
コンテンツを簡潔にし、Q&Aを設け、構造化データを実装し、llms.txtを設置する。これらはすべてAIに「理解」してもらうための重要な戦術です。
でも、忘れてはいけない本質があります。
こうした小手先のテクニックは、AIのアルゴリズムが日々進化する中で、明日には効果が薄れたり、陳腐化したりする可能性が常につきまといます。
しかし、どれだけAIが進化しても、決して陳腐化しない「原理原則」があります。
LLMO対策の本質とは、AIをハックする技術的な試みではなく、AIという新しいプラットフォームの登場によって、より一層鮮明になった「検索の原理原則」に立ち返ることです。
AIファースト vs ユーザーファースト
LLMO対策は、一見すると「AIに最適化する」=「AIファースト」な活動に見えるかもしれません。AIに分かりやすい構造、AIが引用しやすい言葉遣いを意識するわけですからね。
でも、その目的はあくまで、AIという「フィルター」や「翻訳者」を通じて、その先にいる「人間(ユーザー)」に、より速く、より正確に、より価値のある情報を届けることです。結局は「ユーザーファースト」なんです。
AIが理解しやすい「構造」は、多くの場合、人間にとっても分かりやすい構造です。
AIが「信頼できる」と判断するE-E-A-Tや一次情報は、人間にとっても「信頼できる」「役に立つ」情報です。
AIを意識しすぎるあまり、本来の目的である「ユーザーへの価値提供」を忘れてはなりません。AIに媚びるのではなく、AIと「協調」し、AIを通じてユーザーに価値を届ける、というマインドセットが重要です。
私たちが目指すべきゴール
LLMO対策とは、突き詰めれば、
「ユーザーの疑問に対して、最も信頼できる一次情報源となるための、誠実かつ継続的な取り組み」
に他なりません。
AIが理解しやすい「構造」(テクニカル)で、AIがまだ学習していない「独自の情報」(コンテンツ)を、AIが「信頼できる」と客観的に判断できる「E-E-A-T」(権威性)を担保して、提供し続けること。
私たちhakubi codeは、Web制作者として、こうしたテクニカルな実装(構造化データなど)と、本質的なコンテンツ戦略(E-E-A-Tの構築)の両輪から、クライアントのLLMO対策をサポートしていきたいと考えています。
変化の激しいAI時代ですが、この「原理原則」だけは、きっと変わらないはずです。
